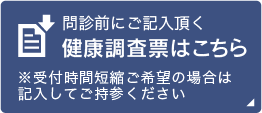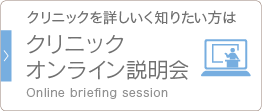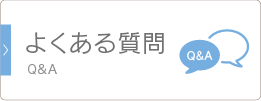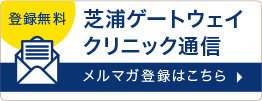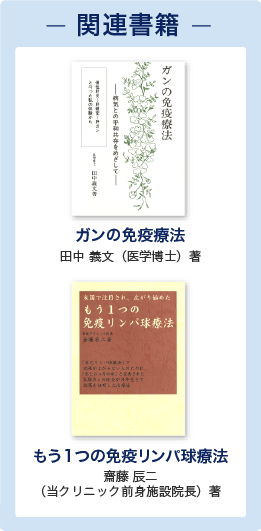膵臓は、自らを溶かす?!
「五臓六腑に染み渡る」という表現があります。
よく使われるのが、喉がカラカラに乾いて、水分補給した時。特に夏の暑い時期のビールをグビグビと飲んだ後に、昭和のおじさん達は言っていました。まぁ、身体中の細胞に染み渡っていくようだという表現ですね。
この「五臓六腑」という言葉は、中国伝統医学において内臓全体を表しているんです。
「臓」とは、細胞がぎっちり詰まっている臓器で、心、肺、肝、脾、腎で五臓。
「腑」とは、中が空洞だったり袋状になっているもので、胃、小腸、大腸、胆嚢、膀胱、そして、普段聞きなれない三焦(さんしょう)です。三焦とは体幹のみぞおちまでを上焦、みぞおちから臍までを中焦、臍から下腹部全体を下焦と言い、その三つのバランスを取ると思われていた機能のことで、一説にはリンパ関係では?とも言われたりしますが、東洋医学の概念なので、現代の医学に無理に当てはめるものではないと、筆者は思います。
さて、耳慣れない三焦に手間取っている場合でなく、ここで一番伝えたいのは五臓の中に「膵臓」が入っていないことなのです!
そもそも東洋医学では、「脾臓」と「脾経」という経絡(気の通り道)を含めた「脾」という概念が、現代でいう「膵臓」の働き全般と考えられていて、何故「膵臓」が「脾臓」になってしまったのかが、筆者が学んだ鍼灸学校でもあまりハッキリ教えてもらえませんでした。
それが、最近になってその理由が分かったのです。「膵臓」を取り上げたTVのサイエンス番組でした。「膵臓」はとても重要な働きをする臓器なのに、何故五臓六腑に膵臓が入っていないかというと、昔はご遺体を解剖するのに、死後早くて2〜3日後、もっ
と後になる場合もあったとかで、解剖しても「膵臓」は溶けて無くなってしまっていたのではないかということでした。
「膵臓」は、胃の後ろにある長さ20cmほどの細長い臓器です。
「膵臓」の働きは、消化液を分泌する外分泌機能と、ホルモンを分泌する内分泌機能を担っています。ここでは、内分泌機能のインスリンなどの働きには触れず、消化液の方にに焦点を絞らせてください。
膵液は膵管から十二指腸内に送られます。膵液には、糖質を分解するアミラーゼ、たんぱく質を分解するトリプシン、脂肪を分解するリパーゼなどの消化酵素、核酸の分解酵素を含んでいて、強い消化能力があります。その強い消化液が自分自身を溶かしてしまう病気が急性膵炎です。恐ろしいですよね。
「膵臓」は、自分を溶かさないように、生きているうちは何らかのリミッターを働かせてているのでしょう。しかし、死亡した後時間が経つとリミッターが外れ、自らを溶かしてしまい、昔の解剖では溶けてしまっていたのだろうということでした。
なるほど、そういう理由で、解剖しても見つからなかったのかと、長年の疑問の答えを得たようで、嬉しくなりました。
それと共に膵液の消化能力の強さに、感服しました。「膵臓」って凄い!
2025年3月 スタッフ 高橋